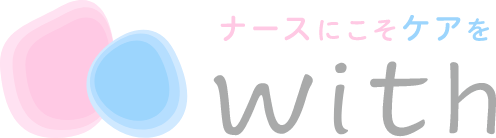医療や看護の現場では、判断に使える情報には限りがあります。
限られた時間、限られた情報の中で、私たちは日々、大切な判断を下しています。
判断には、大きく分けて「直感的な判断」と「意識的な思考による判断」があります。
意識的な思考による判断では、目の前の状況だけでなく、他者の気持ちや考えを想像したり、過去・現在・未来といった時間軸を行き来しながら物事を考えることが求められます(Zeelenberg & Beattie, 1997)。
たくさんの情報を吟味して行う判断には時間がかかりますが、それを重ねていくことで、専門性の高い判断力が育まれます。
また、経験を積むことで、慣れていない人が見落としがちな情報に気づけるようになり、意識的な判断の質も高まっていきます。
しかし、ここには落とし穴もあります。
経験を積むことで、私たちは複雑な情報を抽象化して素早く処理できるようになります。
その反面、つい「経験則」に頼った直感的な判断が増えがちになります。
でも、前提条件が変わっていたり、これまでに出会ったことのない状況だったりすると、その直感が間違った方向に働くこともあります。
直感による判断では、「どの点が正しくて、どの点が誤っていたのか」が見えにくくなったり、自分の直感を裏付ける情報ばかりを集めてしまう傾向(確証バイアス)も出てきます。
そんな状況を防ぐためには——
「自分の判断の確かさ」を、立ち止まって振り返ること。
そして、
他者の考えにふれてみること。
自分の考えを誰かに説明してみること。
それが、判断の質を高める助けになります。
VUCAの時代と呼ばれるいま、医療・看護の現場では、先が読みにくく、難しい判断を求められる場面がますます増えています。
たくさんの情報を集めたけれど、「自分の考えは本当にこれでいいのかな……?」と感じたとき。
ぜひ、「ナースにこそケアをwith」の場をご活用ください。
他者に話してみること、他者の声に耳を傾けてみること——
そのプロセスが、きっとあなたの判断力を支えてくれるはずです。
Zeelenberg, M., & Beattie, J. (1997). Consequences of regret aversion 2: Additional evidence for effects of feedback on decision making. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 72(1), 63-78.
Friedman, C. P., Gatti, G. G., Franz, T. M., Murphy, G. C., Wolf, F. M., Heckerling, P. S., … & Elstein, A. S. (2005). Do physicians know when their diagnoses are correct? Journal of general internal medicine, 20(4), 334-339.